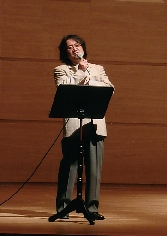|
名古屋フランス音楽研究会 第8回公演 |
||
|
|
||
|
|
フランス音楽史上、バロック音楽はフランス近代音楽と並ぶ重要な頂点の一つです。元来イタリアに端を発したバロック文化は特に音楽の分野で、16世紀末から18世紀にかけてブルボン王朝の栄華と共にフランスで黄金時代を築きました。当時ヴェルサイユ宮殿は芸術的音楽の舞台となり、太陽王ルイ14世をはじめ歴代国王擁護の元、宮廷音楽家達は華々しく活躍したのです。その成果はバレーを組み入れたオペラの音楽形態、室内楽や各楽器そして音楽理論等、あらゆる分野で発展を繰り広げ他のヨーロッパの国々にも影響を与えました。又同時にフランス音楽芸術の基本をも確立したと言えるでしょう。感性と知性のバランスが常に保たれ、繊細優美で色彩感に富み、バロック音楽に多く見られる標題音楽が示すものは自然や人間性への愛と真実への興味であり、そこから描写や表現が生まれています。それらの音楽的特徴は脈々と現代まで受け継がれているのではないでしょうか。今夜はその伝統的エスプリと共に、典雅なるバロック音楽の薫りをリュート演奏から始まり様々な楽器と声楽の調べにのせて皆様にお届けしたいと思います。 |
|
|
|
|
フランスバロック時代の作曲家 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
Prologue プレトーク 「ヨーロッパにおけるフランスバロック」 |
|
||||||||||||||
|
La Musique Française à l’époque
baroque |
|||||||||||||||
|
解説:渡辺 康 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
◆バロック・リュート演奏とお話 |
|
||||||||||||||
|
|
●プレリュード フランソワ・デュフォー |
||||||||||||||
|
|
Prélude François
Du Fault |
||||||||||||||
|
|
●アルマンド「ガロ讃歌」 ロベール・デュ・ヴィゼ |
||||||||||||||
|
|
Allemande “Tombeau de Vieux Gallot”Rober de Visee |
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
Luth Baroque洒井 康雄 |
|||||||||||||||
|
◆フルート演奏 |
|
||||||||||||||
|
●スペインのフォリアによる変奏曲 マラン・マレー |
|||||||||||||||
|
Les Folies D’Espagne
Marin Marais |
|||||||||||||||
|
マラン・マレ(1656-1728)はヴィオール(ヴィオラ・ダ・ガンバ)の名手でありリュリに師事した作曲家。この曲は5巻からなる「ヴィオール曲集」に含まれるヴィオールの為の音楽だが、作曲者自身も「ほとんどの高音楽器で奏せる」と前書きで述べている通りフルートやリコーダーのレパートリーとしても知られている。 |
|||||||||||||||
|
Fl.筧孝也 |
|||||||||||||||
|
◆歌とピアノと弦楽器アンサンブルCantate à une voix avec symphonie |
|
||||||||||||||
|
|
●カンタータ「忠実な羊飼」 ジャン・フィリップ・ラモー |
||||||||||||||
|
|
Le
Berger Fidèle Jean-Philippe Rameau |
||||||||||||||
|
|
詠唱―嘆きのアリア 詠唱―陽気なアリア |
||||||||||||||
|
|
Récitatif-Air plantif Récitatif- Air gai |
||||||||||||||
|
フランスのカンタータは華やかだったが短命で、半世紀間作曲されたに過ぎない。それまでの大規模な音楽悲劇よりもそれを小さくしたサロン的オペラ〈カンタータ〉が好まれ、シャルパンティエを初めにカンプラ、クレランボー続いてラモーが作品を書いた。 ラモーのカンタータには他に「熱望」「オルフェ」「テティス」「アキロンとオリティ」がある。 |
|||||||||||||||
|
Sop.松崎典子Pf.加納優子Vl.竹田千波 |
|||||||||||||||
|
Vl.松浦有希子Vc.中野知子 |
|||||||||||||||
|
◆クラヴサン曲集より |
|
||||||||||||||
|
|
1. ロンド形式のガヴォットGavotte en Rondeau リュリ J.B.Lully |
||||||||||||||
|
|
2. 葦 Les Roseaux クープラン Fr.Couperin |
||||||||||||||
|
|
3. つむじ風 Les Tourbillon ラモー J.Ph. Rameau |
||||||||||||||
|
|
4. カッコウ Le Coucou ダカン L.Cl.Daquin |
||||||||||||||
|
それまでもてはやされたリュートに変わりクラヴサン(チェンバロ)が17世紀後半から18世紀前半迄隆盛期を迎え、宮廷はもとより貴族や豊かな市民階級のサロンを飾った。クラヴサン作曲家の代表的存フランソワ・クープランの作品をみても、フランスバロックにおいて装飾音は重要な表現である。それらを現代のピアノで奏する場合ある種の技術を要するが、立体的描写表現や音色の変化など又違う魅力を発揮出来る。 |
|||||||||||||||
|
Pf.カザボン田島三保子 |
|||||||||||||||
|
◆バロック民謡「羊飼いの歌」よりChanson Folklorique “Bergerettes” |
|
||||||||||||||
|
|
1. エグゾデのメヌエット Menuet d’Exaudet |
||||||||||||||
|
|
2. 私はシダになりたい Que ne suis-je la fougère |
||||||||||||||
|
|
3. 小娘 Jeune Fillette |
||||||||||||||
|
|
4. いいえ、もう森には行きません Non,Je n’irai plus au bois
|
||||||||||||||
|
|
5. ママ、教えて Maman, dites-moi |
||||||||||||||
|
17〜18世紀にかけて歌われた「羊飼い」の世界を題材とした歌で、19世紀後半にパリ音楽院の図書館長J.P.ヴェケランのより収集、出版された。写実派的絵画のような大自然を背景に羊飼いの青年と娘の恋が描かれ、優しくそして時としてエロチックな表現と共に当時の若者達の生活を彷彿とさせる。この曲集出版と平行して、シャブリエ、ドビュッシー、ラヴェル等多くの作曲家によりバロック風の曲が作曲されるようになった。 |
|||||||||||||||
|
18世紀ギター 洒井康雄 Sop.酒井伸代 Guitare Classique (18e siècle ) |
|||||||||||||||
|
◆サクソフォン曲―マルセル・ミュール編曲より |
|
||||||||||||||
|
|
1. アリア Aria ルクレールJ.M.Leclair |
||||||||||||||
|
|
2. 聖霊の踊りOrphée(scène des Champs-élysées) グリュックGluck |
||||||||||||||
|
|
3. 恋のアリアとクーラントAir tendre et Courante リュリJ.P.Lully |
||||||||||||||
|
アリア:ジャン=マリー・ルクレールは、18世紀初頭に活躍したフランス流ヴァイオリン演奏様式の創始者といわれている。たっぷりとしたおだやかな音楽が美しい。 |
|||||||||||||||
|
精霊の踊り:グルックは、オーストリアのオペラ作曲家であるが、1772年〜79年まで度々パリを訪れ活動の本拠とした。この曲はグルックの代表作オペラ「オルフェオ」第2幕中、死者の浄福の国の場面で、その冒頭をかざるバレーのための音楽。 |
|||||||||||||||
|
Pf.竹中勇記彦 Sax.ルマリエ千春 |
|||||||||||||||
|
恋のアリアとクーラント:リュリはイタリア人の貧しい家庭で生まれたのだが、ギーズ公によってパリに連れてこられた。非凡な才能をルイ14世に認められ、王家の楽長となりフランス帰化を果たす。このアリアは、リュリが専門とした宮廷バレーの中の曲で、特にフランス風クーラントは、速度の速い舞曲でリュリの特徴を反映している。本日はソプラノサクソフォンでの演奏。 |
|||||||||||||||
|
◆ チェロとピアノの為の演奏会用小品集 クープラン(ポール・バズレール編曲) |
|
||||||||||||||
|
Fr.Couperin:Pièces en concert pour violoncelle
et quatuor à cordes (Réduction pour violoncelle
et piano)Recueillies, réalisées et
annotées par Paul Bazelair |
|||||||||||||||
|
1. プレリュードPrélude 荘重に |
2. シシリエンヌ Siciliénne やさしく |
||||||||||||||
|
3. ラッパ La tromba 愉快に |
4. 嘆きPlainte 痛みを持って |
||||||||||||||
|
5. 悪魔の歌 Air
de diable 生きいきと |
|
||||||||||||||
|
大クープランと呼ばれているフランソワ・クープランはクラヴサンの並外れた名演奏家であって、クラブサンのショパンともいわれる。彼が残した27集にも及ぶクラヴサンの為のオルドル(組曲)は全く新しい一連の標題(性格:キャラクテール)音楽を歴史に登場させたものである。今夜の作品はパリ・コンセルヴァトワールのチェロ教授ポール・バズレールが5曲を選び小品集としたもの。ランドフスカ音楽論集のクープランの項に「……メランコリーのためのメランコリー。その美しさの詩情、そして又それが与える甘美な包み込むような幸福感のためのメランコリー……」とあるが、共感を覚える。(天野 武子記) |
|||||||||||||||
|
Pf.渡辺理恵子 Violoncelle天野武子 |
|||||||||||||||
|
◆めんどり(ラモー)La
poule J.Ph.Rameau
Arrangement pour piano, flûte, Saxphone, violon et violncellepar Watanabe koh(ラモー作曲:渡辺 康 編曲) ラモー自ら冒頭主題に《コココココココデ》と書き入れ、とにかく鮮やかな鶏の鳴き声の模写はしているが、単なる描写の範囲をはるかに超え、巧みな作曲技巧により劇的な性格に展開される。今夜は渡辺康氏の編曲により五つの楽器のアンサンブルで奏される。 |
|
||||||||||||||
|
Fl.筧 Sax.ルマリエ Pf.竹中 Vl.竹田 Vc.中野 |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||